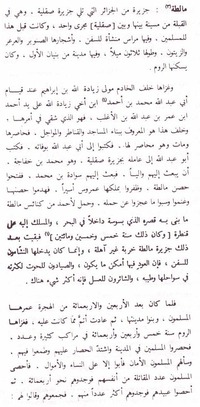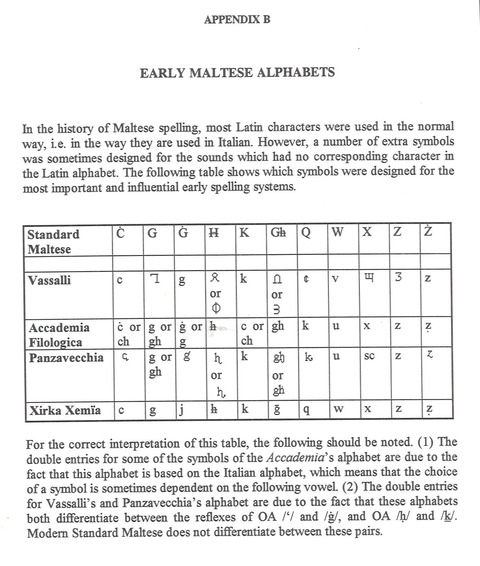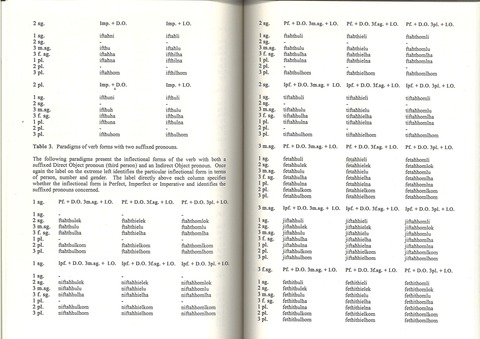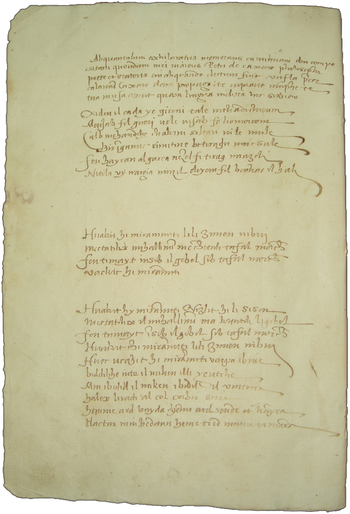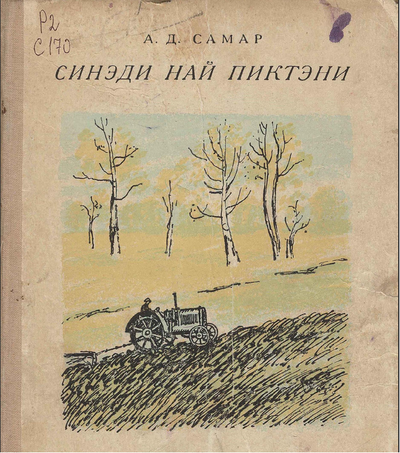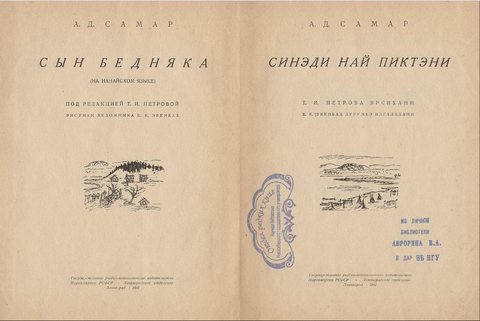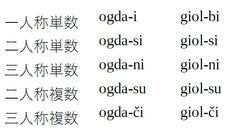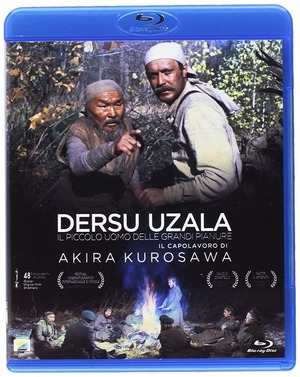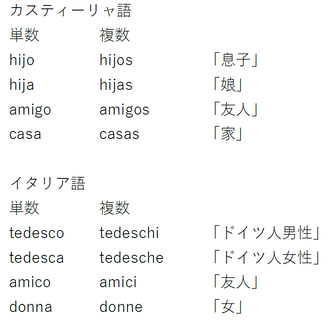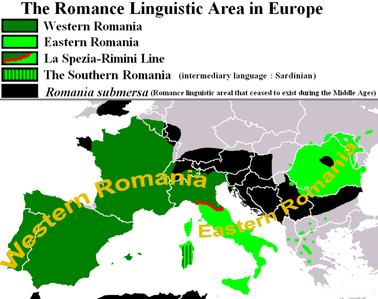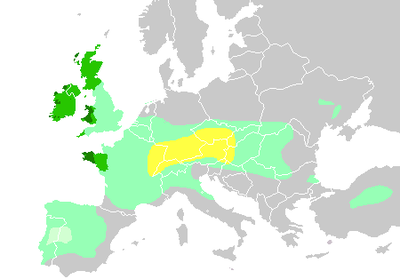英語かドイツ語が母語の人が日本語を勉強していて、「今日は寒くなる」とか「部屋がきれいになりました」と言えずに「今日は寒いなるでしょう」、「部屋がきれいなりました」あるいは「部屋がきれいだなりました」とやっているのを見たことがないだろうか。それぞれ heute wird kalt 、das Zimmer wurde sauber あるいは it will be cold today、the room became clean といった母語での言い方が干渉したのであろう。ドイツ語・英語では「~になる」という文ではコピュラ構造の場合と同じく、述部に形容詞の辞書形がそのまま来るからだ。ウルサイことを言えば例えば「寒い」という形容詞は kalt あるいは cold と等価ではなく、be cold とか kalt sein とかコピュラ付きでいうべきだろう。が一方日本語にはコピュラという動詞がない。「です」だろ「だ」だろは動詞ではなくセンテンスの当該部分にくっ付いてそれがpredicate nounまたはcomplement(ドイツ語でPrädikatsnomen)であることを示す単なるマーカーである。そのPräkatsnomenは格に関しては基本的に中立だから、「です」がつくと格マーカーが削除されることが多い。特に主格マーカーは必ず削除される。「山田さんは先生です」であって絶対「山田さんは先生がです」にはならない。しかしドイツ語のクセを出してこの「です」をコピュラとみなしてしまうと自動的にPräkatsnomenを主格と解釈してしまうことになる。現にドイツ語母語者には「山田さんは今アメリカです」という極簡単なセンテンスが理解できない者がいる。「アメリカ」が処格であることがわからないからだ。ついでに言えば主題の「は」も格は中立だから、主格グセがつくと「その本は昨日読みました」「山田さんは先週お嬢さんに赤ちゃんが生まれました」がわからない。
話を戻すが、そこで「なる」と「です」では全くセンテンスの構造が違い、前者は動詞、後者はマーカーで、動詞「なる」のほうはその補語に形容詞がそのまま来ないで副詞化した形で置かれる、と説明してもドイツ語母語者相手だとまだ十分でないことがある。英語だと簡単だ。日本語では it became beautiful でなくit became beautifullyというんですよと言えばいいが、ドイツ語は形容詞がそのまま副詞になるからだ。Sie ist schön のschön は形容詞で「彼女は美しい」だが、Sie singt schön は「彼女は美しく歌う」でschönが副詞なのに形は全く同じである。gut(形)→ gutØ(副)、schön(形) → schönØ(副)といういわばゼロ付加だ。対して英語には -ly という目に見えるマーカーがつく(beautiful → beautifully )。英語ではさらにゼロマーカーも使うし(cold → coldØ)、語そのものを変換してしまうことがある(good → well)が、ともかく -ly という副詞形成の形態素が存在しているからいい。ドイツ語のように一つの形がいわゆる形容詞と副詞の2つの品詞にまたがっていると、頭ではわかっても気を抜くとすぐ区別が怪しくなる。
そもそも副詞というカテゴリーに入れられているメンバーは形容詞崩れあり前置詞起源のものあり種々雑多で、副詞というのを一つの独立した品詞とみなしていいのかという議論さえあるくらいだ。「つまり動詞でも名詞でも形容詞でもない単語が消去法で副詞として扱われるのだ」と主張する言語学者も少なくないそうだ。カルツェフスキーあたりもそんなことを言っていたらしい。特に形容詞との境界線があいまいで、ヘルマン・パウルでさえこんなことを言っている;
Die formelle Scheidung des Adjektivums vom dem Adv. beruht auf der Flexionsfähigkeit des ersteren und der dadurch ermöglichten Kongruenz mit dem Subst. Wo dies formelle Kriterium entfällt, da kann auch die Scheidung von dem Sprachgefühl nicht mehr strikt aufrecht erhalten werden. ... Wir haben eigentlich kein Recht mehr gut in Sätzen wie er ist gut gekleidet, er spricht gut und gut in Sätzen er ist gut, man hält ihn für gut einander als Adv. und Adj. gegenüberzustellen.
形容詞は副詞と形式上分離させられるが、それは前者が語形変化して名詞と呼応できるという点に基づいている。この基準が満たされなかったりすると言語感覚からしてこの二つをきっちり分ける必要性があまり感じられなくなる。… 本来 er ist gut gekleidet (「彼は良く着飾っている」)、er spricht gut (「彼は上手く話す」)の gut とer ist gut(「彼はいい(人だ)」)、man hält ihn für gut(「皆彼をいい(人だ)と思っている」)という文の gut を副詞対形容詞として対立させて考えなければならない理由はないのだ。
現代ドイツ語文法の権威Dudenでは gut は品詞としては形容詞だが、形容詞には付加語的用法(attributiver Gebrauch)、述語的用法(prädikativer Gebrauch)、副詞的用法(adverbialer Gebrauch)があるとしている。つまり品詞という言語範疇そのものとその機能を分けて考えているわけで、近代言語学的というか説明力が強い。このように機能と形を観念的に区別すると例えば副詞の形容詞的用法というのも成り立つわけで、die Zeitung heute ist interessantという言い回しの副詞 heute がまさにそれであろう。heute は品詞としては副詞だが、ここでは動詞でなく名詞(それともDPとか何とか呼ぶべきか)の die Zeitung(「新聞」)にかかっており、この文は「今日の新聞は面白い」である。
言い換えると品詞そのものが移行するのでなく機能が移行するのである。上述の見方だとgut(形)→ gut(副)はゼロ付加による品詞の転換だが、機能と形を分けるこの考えかただとer singt gut (「彼は上手に歌う」)の gut は形容詞の「転用」と見なせる。日本語ではこれが形容詞の活用として文法化されているのである(いい → よく、寒い → 寒く、きれい → きれいに)。
ロシア語でも形容詞を副詞にするのは一定の形態素の付加による「造語」あるいは「派生」とみなされているようだが、転用、さらには活用と接触する点があって面白い。
文法書をみると形容詞の項に「性質を表す形容詞(Qualitätsadjektiveまたはqualitative Adjektive)からは語尾を -o、-e にすることによって規則的に性質を表す副詞(qualitative Adverbienまたはdeterminative Adverbien)が作られる」とあるし、反対側の副詞の項には「形容詞の語幹から性質を表す副詞を形成するのはロシア語でもドイツ語でもさかんに行なわれている方法である。」と同じことを言っている。詳しくいうと:
1.語幹が硬音子音(非口蓋化音)で終わっている性質形容詞 качественные прилагательные には –о、軟音(口蓋化音)なら –е をつける。
2.-ский、-ской、–цкий、-цкойで終わっている性質形容詞語幹には -и をつける。
3.-ский、-ской、–цкий、-цкойで終わっていても関係形容詞относительные прилагательныеならさらに前に по- をつけ、後ろの -и とで挟む。性質形容詞にもこの型で副詞をつくるものがある。
4.形容詞の女性対格形に в-、за- の前置詞をつける。
5.前置詞に古い短形活用のパラダイムを継続させる。с-、из-、до-+短形生格、 на-、за-+短形対格、по-+短形与格、в-、на-+短形前置詞格を後続させる。
それぞれ次のような例が挙げられる。左に示した形容詞は男性単数主格形、下線部が語幹である。
крайний → крайне(極端な → 極端に)
скорый → наскоро(速やかな → 速やかに)、 новый → заново(新しい → 新しく)、
пустой → попусту(空しい・無駄な → 空しく・無駄に)、
далёкий → вдалеке(遠い → 遠くへ)、 лёгкий → налегке(軽装の → 軽装で)
明確に「造語」と言い切れる英語と違って、ロシア語の形 → 副変換はむしろ文法の範疇に入ることが一見して明らかだ:前綴りとしてあげられている по- や с- などはれっきとした前置詞、つまり独立単語だし、特に4と5で顕著だがその前置詞がきちんと格支配までしている。しかも前置詞が本来の意味を保持している。だから同じдалёкий(「遠い」)という形容詞に из(「~から」)がつくと「遠くから」、в(「~へ」)がつくと「遠くへ」になるのだ。さらにこの形容詞には当然1のパターンのдалекоという副詞もありこれが「遠いところにある」。だからこれらは品詞としての副詞というよりむしろシンタクス上の単位、れっきとした前置詞句PPである。
では1と2はどうか。быстро、 крайнеなど -o、-e で終わる形は形容詞の活用形の一つ短形活用の単数中性形と同じだ。実は私は今までこの быстрый → быстро タイプの副詞化は形容詞の短形中性単数が「転用」されたのものだと思っていた。ところが文法書ではこれが「造語」扱いされているのでむしろ驚いたのである。
ロシア語の形容詞の活用には長形と短形の二つのパラダイムがあり、上でも述べたように形容詞の代表形として挙げてあるのは長形活用の男性単数主格だが、この長形活用形は形容詞一つにつき単数男性、単数中性、単数女性、複数形の4つにそれぞれ主・生・与・対・造・前置の6格あるから理論的には4×6=24形を区別する。「理論的には」と書いたのは複数生格と複数前置格など、同形のものがあるので実際には24より少なくなるからだ。なお、20世紀の初頭までに書かれたロシア語には複数男性・中性と複数女性形を区別しているものがある。前者は語尾が -ые、後者は -ыя となる。例えばкрасивый(「美しい」、男性単数)の主格形は красивая(女性単数)、красивое(中性単数)、красивые(複数)の4つだが、一方男性単数ではкрасивый(主格)、красивого(生格)、красивому(与格)、красивый/красивого(対格)、красивым(造格)、красивом(前置格)という6つの格変化形があるが、中性単数と男性単数は主格と対格以外同形である。上の4で出してある形は女性単数対格である。
対して短形活用のほうは現在では主格形しかないし、形容詞によっては短形を作らないものがある。「美しい」の短形単数男性はкрасив、単数女性がкрасива、単数中性красиво、複数形がкрасивы。語幹が口蓋化音で終わると女性、中性、複数形がそれぞれ-я、-е、-и で終わる。しかし上で「現在では」と但し書きをつけたように、昔はこの短形が長形と同じくフルバージョンで活用し、名詞と全く同じ活用語尾をとった。上の5を見てもらいたい。形容詞が短形中性単数形の格変化形を完全に供えているのがわかる。1の -o、-e も中性単数の活用語尾ではないのか。英語の -ly とは違って造語・派生形態素ではなく活用語尾、形 → 副の転換は形容詞の一つの活用形をシステマティックに転用したもの、という気がしてならない。さらにこれらは中性単数主格なのではなく実は対格なのではないかと私は疑っている。
問題は2、3のタイプ、-ский などで終わる形容詞で、これらに -и がつくのはどうしてかちょっと調べてみたがわからなかった。落ちこぼれロシア語学習者で申し訳ないが、落ちこぼれなりに考えてみると、このタイプの形容詞は名詞から派生してきたもの、つまり形容詞としては新参者が多い。だから5と違って形容詞が中性名詞的に働くことが出来ず、付加語としての陰を引きずっているのかもしれない。言い換えると昔は後ろに「様式」とか「やり方」を表す名詞がくっついていたのかもしれないとも思ったがこれがあまり上手く行かない:現在は「やり方」はобразという男性名詞で、形容詞を無理やり短形パラダイムにすると「創造的に」はпо творческу образу となるはずで -и が出てこないからだ。では昔はобраз という意味の女性名詞があったのかと解釈しても、与格支配の по とは合わない。では少なくとも2は複数対格かあるいは女性単数生格か複数対格起源だとして逃げようとしても3の例が残るので逃げ切れない。やっぱり -и となる理由が考えつかないまま堂々巡りである。
やはり素直に-o、-e、-и は派生の形態素とみるしかないのか。
話を戻すが、そこで「なる」と「です」では全くセンテンスの構造が違い、前者は動詞、後者はマーカーで、動詞「なる」のほうはその補語に形容詞がそのまま来ないで副詞化した形で置かれる、と説明してもドイツ語母語者相手だとまだ十分でないことがある。英語だと簡単だ。日本語では it became beautiful でなくit became beautifullyというんですよと言えばいいが、ドイツ語は形容詞がそのまま副詞になるからだ。Sie ist schön のschön は形容詞で「彼女は美しい」だが、Sie singt schön は「彼女は美しく歌う」でschönが副詞なのに形は全く同じである。gut(形)→ gutØ(副)、schön(形) → schönØ(副)といういわばゼロ付加だ。対して英語には -ly という目に見えるマーカーがつく(beautiful → beautifully )。英語ではさらにゼロマーカーも使うし(cold → coldØ)、語そのものを変換してしまうことがある(good → well)が、ともかく -ly という副詞形成の形態素が存在しているからいい。ドイツ語のように一つの形がいわゆる形容詞と副詞の2つの品詞にまたがっていると、頭ではわかっても気を抜くとすぐ区別が怪しくなる。
そもそも副詞というカテゴリーに入れられているメンバーは形容詞崩れあり前置詞起源のものあり種々雑多で、副詞というのを一つの独立した品詞とみなしていいのかという議論さえあるくらいだ。「つまり動詞でも名詞でも形容詞でもない単語が消去法で副詞として扱われるのだ」と主張する言語学者も少なくないそうだ。カルツェフスキーあたりもそんなことを言っていたらしい。特に形容詞との境界線があいまいで、ヘルマン・パウルでさえこんなことを言っている;
Die formelle Scheidung des Adjektivums vom dem Adv. beruht auf der Flexionsfähigkeit des ersteren und der dadurch ermöglichten Kongruenz mit dem Subst. Wo dies formelle Kriterium entfällt, da kann auch die Scheidung von dem Sprachgefühl nicht mehr strikt aufrecht erhalten werden. ... Wir haben eigentlich kein Recht mehr gut in Sätzen wie er ist gut gekleidet, er spricht gut und gut in Sätzen er ist gut, man hält ihn für gut einander als Adv. und Adj. gegenüberzustellen.
形容詞は副詞と形式上分離させられるが、それは前者が語形変化して名詞と呼応できるという点に基づいている。この基準が満たされなかったりすると言語感覚からしてこの二つをきっちり分ける必要性があまり感じられなくなる。… 本来 er ist gut gekleidet (「彼は良く着飾っている」)、er spricht gut (「彼は上手く話す」)の gut とer ist gut(「彼はいい(人だ)」)、man hält ihn für gut(「皆彼をいい(人だ)と思っている」)という文の gut を副詞対形容詞として対立させて考えなければならない理由はないのだ。
現代ドイツ語文法の権威Dudenでは gut は品詞としては形容詞だが、形容詞には付加語的用法(attributiver Gebrauch)、述語的用法(prädikativer Gebrauch)、副詞的用法(adverbialer Gebrauch)があるとしている。つまり品詞という言語範疇そのものとその機能を分けて考えているわけで、近代言語学的というか説明力が強い。このように機能と形を観念的に区別すると例えば副詞の形容詞的用法というのも成り立つわけで、die Zeitung heute ist interessantという言い回しの副詞 heute がまさにそれであろう。heute は品詞としては副詞だが、ここでは動詞でなく名詞(それともDPとか何とか呼ぶべきか)の die Zeitung(「新聞」)にかかっており、この文は「今日の新聞は面白い」である。
言い換えると品詞そのものが移行するのでなく機能が移行するのである。上述の見方だとgut(形)→ gut(副)はゼロ付加による品詞の転換だが、機能と形を分けるこの考えかただとer singt gut (「彼は上手に歌う」)の gut は形容詞の「転用」と見なせる。日本語ではこれが形容詞の活用として文法化されているのである(いい → よく、寒い → 寒く、きれい → きれいに)。
ロシア語でも形容詞を副詞にするのは一定の形態素の付加による「造語」あるいは「派生」とみなされているようだが、転用、さらには活用と接触する点があって面白い。
文法書をみると形容詞の項に「性質を表す形容詞(Qualitätsadjektiveまたはqualitative Adjektive)からは語尾を -o、-e にすることによって規則的に性質を表す副詞(qualitative Adverbienまたはdeterminative Adverbien)が作られる」とあるし、反対側の副詞の項には「形容詞の語幹から性質を表す副詞を形成するのはロシア語でもドイツ語でもさかんに行なわれている方法である。」と同じことを言っている。詳しくいうと:
1.語幹が硬音子音(非口蓋化音)で終わっている性質形容詞 качественные прилагательные には –о、軟音(口蓋化音)なら –е をつける。
2.-ский、-ской、–цкий、-цкойで終わっている性質形容詞語幹には -и をつける。
3.-ский、-ской、–цкий、-цкойで終わっていても関係形容詞относительные прилагательныеならさらに前に по- をつけ、後ろの -и とで挟む。性質形容詞にもこの型で副詞をつくるものがある。
4.形容詞の女性対格形に в-、за- の前置詞をつける。
5.前置詞に古い短形活用のパラダイムを継続させる。с-、из-、до-+短形生格、 на-、за-+短形対格、по-+短形与格、в-、на-+短形前置詞格を後続させる。
それぞれ次のような例が挙げられる。左に示した形容詞は男性単数主格形、下線部が語幹である。
1.
быстрый → быстро(速い → 速く)、красивый → красиво(美しい → 美しく)
односторонний → односторонне(一面的な → 一面的に)、крайний → крайне(極端な → 極端に)
2.
творческий → творчески(創造的な → 創造的に)、
дружеский → дружески(親しげな → 親しげに)3.
русский → по-русски(ロシアの → ロシア風に・ロシア語で)
4.
крутой → вкрутую(堅い → 堅く)(卵の茹で方に関してのみ)、
частый → зачастую(頻繁な → 頻繁に)(частоという1のパターンの造語も可)5.
новый → снова(新しい → 新しく・もう一度始めから)、
далёкий → издалека(遠い → 遠くから)、сытый → досыта(満腹な → 満腹に)、скорый → наскоро(速やかな → 速やかに)、 новый → заново(新しい → 新しく)、
пустой → попусту(空しい・無駄な → 空しく・無駄に)、
далёкий → вдалеке(遠い → 遠くへ)、 лёгкий → налегке(軽装の → 軽装で)
明確に「造語」と言い切れる英語と違って、ロシア語の形 → 副変換はむしろ文法の範疇に入ることが一見して明らかだ:前綴りとしてあげられている по- や с- などはれっきとした前置詞、つまり独立単語だし、特に4と5で顕著だがその前置詞がきちんと格支配までしている。しかも前置詞が本来の意味を保持している。だから同じдалёкий(「遠い」)という形容詞に из(「~から」)がつくと「遠くから」、в(「~へ」)がつくと「遠くへ」になるのだ。さらにこの形容詞には当然1のパターンのдалекоという副詞もありこれが「遠いところにある」。だからこれらは品詞としての副詞というよりむしろシンタクス上の単位、れっきとした前置詞句PPである。
では1と2はどうか。быстро、 крайнеなど -o、-e で終わる形は形容詞の活用形の一つ短形活用の単数中性形と同じだ。実は私は今までこの быстрый → быстро タイプの副詞化は形容詞の短形中性単数が「転用」されたのものだと思っていた。ところが文法書ではこれが「造語」扱いされているのでむしろ驚いたのである。
ロシア語の形容詞の活用には長形と短形の二つのパラダイムがあり、上でも述べたように形容詞の代表形として挙げてあるのは長形活用の男性単数主格だが、この長形活用形は形容詞一つにつき単数男性、単数中性、単数女性、複数形の4つにそれぞれ主・生・与・対・造・前置の6格あるから理論的には4×6=24形を区別する。「理論的には」と書いたのは複数生格と複数前置格など、同形のものがあるので実際には24より少なくなるからだ。なお、20世紀の初頭までに書かれたロシア語には複数男性・中性と複数女性形を区別しているものがある。前者は語尾が -ые、後者は -ыя となる。例えばкрасивый(「美しい」、男性単数)の主格形は красивая(女性単数)、красивое(中性単数)、красивые(複数)の4つだが、一方男性単数ではкрасивый(主格)、красивого(生格)、красивому(与格)、красивый/красивого(対格)、красивым(造格)、красивом(前置格)という6つの格変化形があるが、中性単数と男性単数は主格と対格以外同形である。上の4で出してある形は女性単数対格である。
対して短形活用のほうは現在では主格形しかないし、形容詞によっては短形を作らないものがある。「美しい」の短形単数男性はкрасив、単数女性がкрасива、単数中性красиво、複数形がкрасивы。語幹が口蓋化音で終わると女性、中性、複数形がそれぞれ-я、-е、-и で終わる。しかし上で「現在では」と但し書きをつけたように、昔はこの短形が長形と同じくフルバージョンで活用し、名詞と全く同じ活用語尾をとった。上の5を見てもらいたい。形容詞が短形中性単数形の格変化形を完全に供えているのがわかる。1の -o、-e も中性単数の活用語尾ではないのか。英語の -ly とは違って造語・派生形態素ではなく活用語尾、形 → 副の転換は形容詞の一つの活用形をシステマティックに転用したもの、という気がしてならない。さらにこれらは中性単数主格なのではなく実は対格なのではないかと私は疑っている。
問題は2、3のタイプ、-ский などで終わる形容詞で、これらに -и がつくのはどうしてかちょっと調べてみたがわからなかった。落ちこぼれロシア語学習者で申し訳ないが、落ちこぼれなりに考えてみると、このタイプの形容詞は名詞から派生してきたもの、つまり形容詞としては新参者が多い。だから5と違って形容詞が中性名詞的に働くことが出来ず、付加語としての陰を引きずっているのかもしれない。言い換えると昔は後ろに「様式」とか「やり方」を表す名詞がくっついていたのかもしれないとも思ったがこれがあまり上手く行かない:現在は「やり方」はобразという男性名詞で、形容詞を無理やり短形パラダイムにすると「創造的に」はпо творческу образу となるはずで -и が出てこないからだ。では昔はобраз という意味の女性名詞があったのかと解釈しても、与格支配の по とは合わない。では少なくとも2は複数対格かあるいは女性単数生格か複数対格起源だとして逃げようとしても3の例が残るので逃げ切れない。やっぱり -и となる理由が考えつかないまま堂々巡りである。
やはり素直に-o、-e、-и は派生の形態素とみるしかないのか。