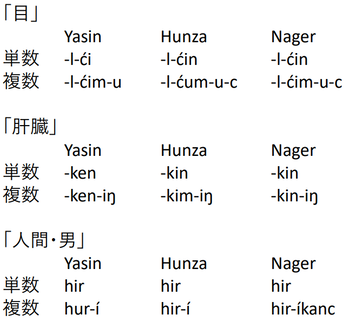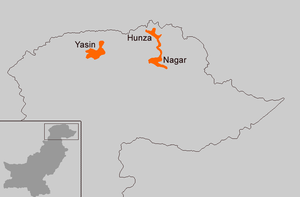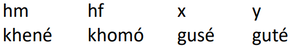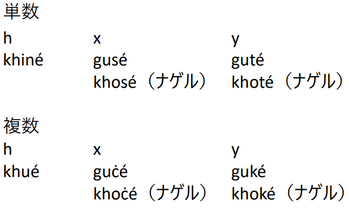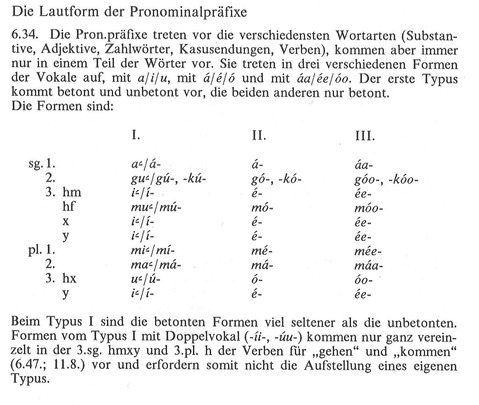日本の憲法9条は次のようになっている。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この文面で一番面白いのは「これ」という指示代名詞の使い方である(太字)。3つあるが、全て「を」という対格マーカーがついており、「は」をつけて表された先行するセンテンス・トピック、それぞれ「武力による威嚇又は武力の行使」、「陸海空軍その他の戦力」、「国の交戦権」(下線部)を指示し、そのトピック要素の述部のシンタクス構造内での位置を明確にしている。
こういう指示代名詞をresumptive pronounsと呼んでいるが、その研究が一番盛んなのは英語学であろう。すでに生成文法のGB理論のころからやたらとたくさんの論文が出ている。その多くが関係節relative clauseがらみである。例えばE.Princeという人があげている、
...the man who this made feel him sad …
という文(の一部)ではwho がすでにthe manにかかっているのに、関係節に再び him(太字)という代名詞が現れてダブっている。これがresumptive pronounである。
しかし上の日本語の文章は関係文ではなく、いわゆるleft-dislocationといわれる構文だ。実は私は英語が超苦手で英文法なんて恐竜時代に書かれたRadford(『43.いわゆる入門書について』参照)の古本しか持っていないのだがそこにもleft-dislocationの例が出ている。ちょっとそれを変更して紹介すると、まず
I really hate Bill.
という文は目的語の場所を動かして
1.Bill I really hate.
2.Bill, I really hate him.
と二通りにアレンジできる。2ではhimというresumptive pronounが使われているのがわかるだろう。1は英文法でtopicalization、2がleft-dislocationと呼ばれる構文である。どちらも文の中のある要素(ここではBill)がmoveαという文法上の操作によって文頭に出てくる現象であるが、「文頭」という表面上の位置は同じでも深層ではBillの位置が異なる。その証拠に、2では前に出された要素と文本体との間にmanという間投詞を挟むことができるが、1ではできない。
1.*Bill, man, I really hate.
2.Bill, man, I really hate him.
Radfordによれば、Billの文構造上の位置は1ではC-specifier、2では CP adjunctとのことである。しっかし英語というのは英語そのものより文法用語のほうがよっぽど難しい。以前『78.「体系」とは何か』でも書いたがこんな用語で説明してもらうくらいならそれこそおバカな九官鳥に徹して文法なんてすっ飛ばして「覚えましょう作戦」を展開したほうが楽そうだ。
さらに英文法用語は難しいばかりでなく、日本人から見るとちょっと待てと思われるものがあるから厄介だ。例えば最初の1を単純にtopicalizationと一絡げにしていいのか。というのも、1のセンテンスは2通りのアクセントで発音でき、日本語に訳してみるとそれぞれ意味がまったく違っていることがわかるからだ。
一つはBillをいわゆるトピック・アクセントと呼ばれるニョロニョロしたアクセントというかイントネーションで発音するもの。これは日本語で
ビルはマジ嫌いだよ。
となる。例えば「君、ビルをどう思う?」と聞かれた場合はこういう答えになる。もう一つはBillに強勢というかフォーカスアクセントを置くやり方で、
ビルが嫌いなんだよ。
である。「君、ヒラリーが嫌いなんだって?」といわれたのを訂正する時のイントネーションだ。つまり上の1はtopicalizationとはいいながら全く別の情報構造を持った別のセンテンスなのだ。
対して2のresumptive pronounつきのleft-dislocation文はトピックアクセントで発音するしかない。言い換えると「ビルは」という解釈しかできないのである。英語に関しては本で読んだだけだったので、同じ事をドイツ語でネイティブ実験してみた。近くに英語ネイティブがいなかったのでドイツ語で代用したのである。ドイツ語では1と2の文はそれぞれ
1.Willy hasse ich.
2.Willy, ich hasse ihn.
だが、披験者に「君はヴィリィをどう思うと聞かれて「Willy hasse ich.」と答えられるか?」と聞いたら「うん」。続いて「「君はオスカーが嫌いなんだろ」といわれて「Willy hasse ich.」といえるか?」(もちろんイントネーションに気をつけて質問を行なった(つもり))と聞くとやっぱり「うん」。次に「君はヴィリィをどう思う?」「Willy, ich hasse ihn.」という会話はあり得るか、という質問にも「うん」。ところが「君はオスカーが嫌いなんだろ?」「Willy, ich hasse ihn.」という会話は「成り立たない」。英語と同じである。つまりleft-dislocationされた要素はセンテンストピックでしかありえないのだ。だから上の日本語の文でも先行詞に全部トピックマーカーの「は」がついているのである。
さらにここでRonnie Cann, Tami Kaplan, Tuth Kempsonという学者がその共同論文で「成り立たない」としているresumptive pronoun構造を見てみると面白い。
*Which book did John read it?
*Every book, John read it.
Cann氏らはこれをシンタクス構造、または論理面から分析しているが、スリル満点なことに、これらの「不可能なleft-dislocation構造」はどちらも日本語に訳すと当該要素に「は」がつけられないのである。
* どの本はジョンが読みましたか?
* 全ての本はジョンが読みました。
というわけで、このleft-dislocationもtopicalizationもシンタクス構造面ばかりではなく、センテンスの情報構造面からも分析したほうがいいんじゃね?という私の考えはあながち「落ちこぼれ九官鳥の妄想」と一笑に付すことはできないのではないだろうか。
さて日本国憲法の話に戻るが、トピックマーカーの形態素を持つ日本語と違って英語ドイツ語ではセンテンストピックを表すのにイントネーションなどの助けを借りるしかなく、畢竟文字で書かれたテキストでは当該要素がトピックであると「確実に目でわかる」ようにleft-dislocation、つまりresumptive pronounを使わざるを得ないが、日本語は何もそんなもん持ち出さなくてもトピックマーカーの「は」だけで用が足りる。日本国憲法ではいちいち「これを」というresumptive pronounが加えてあるが、ナシでもよろしい。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない。
これで十分に通じるのにどうしてあんなウザイ代名詞を連発使用したのか。漢文や文語の影響でついああなってしまったのか、硬い文章にしてハク付け・カッコ付けするため英語・ドイツ語のサルマネでもしてわざとやったのか。後者の可能性が高い。憲法の内容なんかよりこの代名詞の使い方のほうをよっぽど変更してほしい。
もう一つ、英文法でのセンテンストピックの扱いには日本人として一言ある人が多いだろう。英文法ではセンテンストピックは、上でも述べたように深層構造(最近の若い人はD-構造とか呼んでいるようだが)にあった文の一要素が文頭、というより樹形図でのより高い文構造の位置にしゃしゃり出てきたものだと考える。つまりセンテンストピックとは本質的に「文の中の一要素」なのである。
これに対して疑問を投げかけたというか反証したというかガーンと一発言ってやったのが元ハーバード大の久野暲教授で、センテンストピックと文本体には理論的にはシンタクス上のつながりは何もなく、文本体とトピックのシンタクス上のつながりがあるように見えるとしたらそれは聞き手が談話上で初めて行なった解釈に過ぎない、と主張した。教授はその根拠として
太朗は花子が家出した。
という文を挙げている。この文は部外者が聞いたら「全くセンテンスになっていない」としてボツを食らわすだろうが、「花子と太朗が夫婦である」ことを知っている人にとっては完全にOKだというのである。この論文は生成文法がまだGB理論であったころにすでに発表されていて、私が読んだのはちょっと後になってからだが(それでももう随分と昔のことだ)、ゴチャゴチャダラダラ樹形図を描いてセンテンストピックの描写をしている論文群にやや食傷していたところにこれを読んだときの爽快感をいまだに覚えている。
とにかくこのleft-dislocation だろtopicalizationだろ resumptive pronounだろについては研究論文がイヤというほど出ているから興味のある方は読んで見られてはいかがだろうか。私はパスさせてもらうが。
この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。

人気ブログランキングへ
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この文面で一番面白いのは「これ」という指示代名詞の使い方である(太字)。3つあるが、全て「を」という対格マーカーがついており、「は」をつけて表された先行するセンテンス・トピック、それぞれ「武力による威嚇又は武力の行使」、「陸海空軍その他の戦力」、「国の交戦権」(下線部)を指示し、そのトピック要素の述部のシンタクス構造内での位置を明確にしている。
こういう指示代名詞をresumptive pronounsと呼んでいるが、その研究が一番盛んなのは英語学であろう。すでに生成文法のGB理論のころからやたらとたくさんの論文が出ている。その多くが関係節relative clauseがらみである。例えばE.Princeという人があげている、
...the man who this made feel him sad …
という文(の一部)ではwho がすでにthe manにかかっているのに、関係節に再び him(太字)という代名詞が現れてダブっている。これがresumptive pronounである。
しかし上の日本語の文章は関係文ではなく、いわゆるleft-dislocationといわれる構文だ。実は私は英語が超苦手で英文法なんて恐竜時代に書かれたRadford(『43.いわゆる入門書について』参照)の古本しか持っていないのだがそこにもleft-dislocationの例が出ている。ちょっとそれを変更して紹介すると、まず
I really hate Bill.
という文は目的語の場所を動かして
1.Bill I really hate.
2.Bill, I really hate him.
と二通りにアレンジできる。2ではhimというresumptive pronounが使われているのがわかるだろう。1は英文法でtopicalization、2がleft-dislocationと呼ばれる構文である。どちらも文の中のある要素(ここではBill)がmoveαという文法上の操作によって文頭に出てくる現象であるが、「文頭」という表面上の位置は同じでも深層ではBillの位置が異なる。その証拠に、2では前に出された要素と文本体との間にmanという間投詞を挟むことができるが、1ではできない。
1.*Bill, man, I really hate.
2.Bill, man, I really hate him.
Radfordによれば、Billの文構造上の位置は1ではC-specifier、2では CP adjunctとのことである。しっかし英語というのは英語そのものより文法用語のほうがよっぽど難しい。以前『78.「体系」とは何か』でも書いたがこんな用語で説明してもらうくらいならそれこそおバカな九官鳥に徹して文法なんてすっ飛ばして「覚えましょう作戦」を展開したほうが楽そうだ。
さらに英文法用語は難しいばかりでなく、日本人から見るとちょっと待てと思われるものがあるから厄介だ。例えば最初の1を単純にtopicalizationと一絡げにしていいのか。というのも、1のセンテンスは2通りのアクセントで発音でき、日本語に訳してみるとそれぞれ意味がまったく違っていることがわかるからだ。
一つはBillをいわゆるトピック・アクセントと呼ばれるニョロニョロしたアクセントというかイントネーションで発音するもの。これは日本語で
ビルはマジ嫌いだよ。
となる。例えば「君、ビルをどう思う?」と聞かれた場合はこういう答えになる。もう一つはBillに強勢というかフォーカスアクセントを置くやり方で、
ビルが嫌いなんだよ。
である。「君、ヒラリーが嫌いなんだって?」といわれたのを訂正する時のイントネーションだ。つまり上の1はtopicalizationとはいいながら全く別の情報構造を持った別のセンテンスなのだ。
対して2のresumptive pronounつきのleft-dislocation文はトピックアクセントで発音するしかない。言い換えると「ビルは」という解釈しかできないのである。英語に関しては本で読んだだけだったので、同じ事をドイツ語でネイティブ実験してみた。近くに英語ネイティブがいなかったのでドイツ語で代用したのである。ドイツ語では1と2の文はそれぞれ
1.Willy hasse ich.
2.Willy, ich hasse ihn.
だが、披験者に「君はヴィリィをどう思うと聞かれて「Willy hasse ich.」と答えられるか?」と聞いたら「うん」。続いて「「君はオスカーが嫌いなんだろ」といわれて「Willy hasse ich.」といえるか?」(もちろんイントネーションに気をつけて質問を行なった(つもり))と聞くとやっぱり「うん」。次に「君はヴィリィをどう思う?」「Willy, ich hasse ihn.」という会話はあり得るか、という質問にも「うん」。ところが「君はオスカーが嫌いなんだろ?」「Willy, ich hasse ihn.」という会話は「成り立たない」。英語と同じである。つまりleft-dislocationされた要素はセンテンストピックでしかありえないのだ。だから上の日本語の文でも先行詞に全部トピックマーカーの「は」がついているのである。
さらにここでRonnie Cann, Tami Kaplan, Tuth Kempsonという学者がその共同論文で「成り立たない」としているresumptive pronoun構造を見てみると面白い。
*Which book did John read it?
*Every book, John read it.
Cann氏らはこれをシンタクス構造、または論理面から分析しているが、スリル満点なことに、これらの「不可能なleft-dislocation構造」はどちらも日本語に訳すと当該要素に「は」がつけられないのである。
* どの本はジョンが読みましたか?
* 全ての本はジョンが読みました。
というわけで、このleft-dislocationもtopicalizationもシンタクス構造面ばかりではなく、センテンスの情報構造面からも分析したほうがいいんじゃね?という私の考えはあながち「落ちこぼれ九官鳥の妄想」と一笑に付すことはできないのではないだろうか。
さて日本国憲法の話に戻るが、トピックマーカーの形態素を持つ日本語と違って英語ドイツ語ではセンテンストピックを表すのにイントネーションなどの助けを借りるしかなく、畢竟文字で書かれたテキストでは当該要素がトピックであると「確実に目でわかる」ようにleft-dislocation、つまりresumptive pronounを使わざるを得ないが、日本語は何もそんなもん持ち出さなくてもトピックマーカーの「は」だけで用が足りる。日本国憲法ではいちいち「これを」というresumptive pronounが加えてあるが、ナシでもよろしい。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない。
これで十分に通じるのにどうしてあんなウザイ代名詞を連発使用したのか。漢文や文語の影響でついああなってしまったのか、硬い文章にしてハク付け・カッコ付けするため英語・ドイツ語のサルマネでもしてわざとやったのか。後者の可能性が高い。憲法の内容なんかよりこの代名詞の使い方のほうをよっぽど変更してほしい。
もう一つ、英文法でのセンテンストピックの扱いには日本人として一言ある人が多いだろう。英文法ではセンテンストピックは、上でも述べたように深層構造(最近の若い人はD-構造とか呼んでいるようだが)にあった文の一要素が文頭、というより樹形図でのより高い文構造の位置にしゃしゃり出てきたものだと考える。つまりセンテンストピックとは本質的に「文の中の一要素」なのである。
これに対して疑問を投げかけたというか反証したというかガーンと一発言ってやったのが元ハーバード大の久野暲教授で、センテンストピックと文本体には理論的にはシンタクス上のつながりは何もなく、文本体とトピックのシンタクス上のつながりがあるように見えるとしたらそれは聞き手が談話上で初めて行なった解釈に過ぎない、と主張した。教授はその根拠として
太朗は花子が家出した。
という文を挙げている。この文は部外者が聞いたら「全くセンテンスになっていない」としてボツを食らわすだろうが、「花子と太朗が夫婦である」ことを知っている人にとっては完全にOKだというのである。この論文は生成文法がまだGB理論であったころにすでに発表されていて、私が読んだのはちょっと後になってからだが(それでももう随分と昔のことだ)、ゴチャゴチャダラダラ樹形図を描いてセンテンストピックの描写をしている論文群にやや食傷していたところにこれを読んだときの爽快感をいまだに覚えている。
とにかくこのleft-dislocation だろtopicalizationだろ resumptive pronounだろについては研究論文がイヤというほど出ているから興味のある方は読んで見られてはいかがだろうか。私はパスさせてもらうが。
この記事は身の程知らずにもランキングに参加しています(汗)。
人気ブログランキングへ